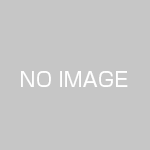[第一部]東京からデリー・アグラを経て、ベナレス・サールナートへ
(2006年7月15日~31日)
一
すべての神聖なものは夢や思い出と同じ要素から成立ち、時間や空間によってわれわれと隔てられているものが、現前していることの奇蹟だから。しかもそれら三つは、いずれも手で触れることのできない点でも共通している。手で触れることのできたものから、一歩遠ざかると、もうそれは神聖なものになり、奇蹟になり、ありえないような美しいものになる。事物にはすべて神聖さが具わっているのに、われわれの指に触れるから、それは汚濁になってしまう。われわれ人間は不思議な存在だ。指で触れるかぎりのものを穢(けが)し、しかも自分のなかには、神聖なものになりうる素質を持っているのだから。「春の雪(豊穣の海・第一部)/三島由紀夫」より
二

アグラ駅のホームで列車を待っていると、薄汚れたシャツを着て汗にまみれたインド人ポーターが、「お前はタバコを吸うのか?」と聞いてきた。
「吸うよ」と言う変わりに、日本から持ってきた赤いマルボロを見せると、「これを吸ってみろ」と、細くてしわくちゃなインドのタバコをくれた。
不味くはないがマリファナのような、なんとも言えない味がする。
やがて列車はホームに到着し、ポーターの誘導で自分のシートに辿り着くことが出来た。
ポーターは当たり前のように「チップをくれ」という。
二十ルピー札(五十二円)を渡すと、怪訝な表情で突き返された。
チップとしては安すぎたのかと思い、百ルピー札(二百六十円)を渡し直すと、男は礼も言わず黙って立ち去っていった。

予約していた席は、クーラー付きの二等。
一つのコンパートメントに四人が座れる寝台列車だ。
席に座ると、間もなく西洋人の女性ばかりの団体客が自分の周りを埋めていった。
どうやら、その団体客の中にぽつんと自分の席があるようだ。
女性たちの話す言葉を聞くと英語ではない。
しばらくその様子を見ていると、その中の一人が話し掛けてきた。
「自分だけ少し離れた場所の座席にリザーブされているので、もしよければ席を換わってくれないか?」
断る理由もなかったので、快く引き受けた。
どこの国から来たのかと尋ねると、スペインからということだった。
サンキュー!サンキュー!という他のスパニッシュ達の声に見送られながら、声を掛けてきた女性に案内されて新しい席に行くと、クルタと言われる白い民族衣装を着たインド人が二人居た。
そこは、華やかなスパニッシュ達がいたコンパートメントとはまるで違う、厳かでかつ近寄りがたい雰囲気だった。
インドの列車は到着駅のアナウンスもなく、今どこの駅にいるのか全く分からない。
乗り過ごすとそれこそどうしようもない。
仕方なく同じ席のインド人に頼むことにした。
「もしベナレス駅まで行くなら、悪いが着いたら起こしてくれないか?」
「自分達はカルカッタまで行く。ベナレスには何時に着くんだ?」
「多分朝の九時頃だと思う」
「それは違うだろう」
インド人に険しい表情でそう言われると、何も言えなくなってしまった。
インド人に頼むのは諦めて、先程のスパニッシュ達にお願いすることにした。
彼女達もベナレスに行くと言ってたからだ。
「ベナレスに着いてまだ寝てたら起こしてください」と言いに行くと、皆で「オーケー!オーケー!」と快諾してくれた。
ヨーロッパ人は愛想が良くて素晴らしい。
インドでは幾つかの難関があると思っていた。
最初の難関は、デリーの空港に送迎が来てくれるかどうかということ。
次は、ちゃんと列車に乗り、目的の駅で降りることが出来るかということだった。
スペイン人女性たちの快諾を得てすっかり安心した。そして、一人寝台の上で、日本から持ってきていた梅干と柿の種をつまみながら、これから始まる旅に思いを馳せていた。

三
インドへは成田経由で出発した。
成田空港の滑走路を走る機中で、今から離陸し、着陸する地のことを想うと、まさにこれからジェットコースターの一番高みへと昇り、インドという空恐ろしい地へ急降下していくような恐怖心が沸き起こってきた。
なぜこんな恐怖を味わうためにこのジェットコースターに乗ってしまったのだろうか、今ならまだ引き返せるかもしれない。
しかし、既に機は離陸体制に入っている。
恐怖を抱いて離陸するしかもう為す術がなかった。
何故インドに行きたいと思ったのだろうか。
改めて自問してみても、誰もが納得できるような返答をする自信はない。
後にブッダガヤの町で出会った女性に、
「心の奥底に大きなコンプレックスがあり、それを取り除くともっと自由になれる」と言われたように、混沌の国インドでそのコンプレックスを取り除きたかったのだろうか?
藤原新也のインド写真集「メメント・モリ」に書かれていた(人間は犬に喰われるほど自由だ)という言葉や、バックパッカーのバイブルと言われる沢木耕太郎の「深夜特急」の一文にある(自分の中の何かから、一つ、また一つと自由になっていった)のように、自由になりたかったからだろうか?
自由ではないと感じていたのだろうか?今となっては分からない。
しかし、二十代前半の感性の液体が煮詰まり、今は「インドに行く」という固形の目的だけが目の前にあるが、そこには様々なコンプレックスや悩み、また憧れや願望など、真理を知りたい学びたいという、様々な目論見が凝縮されていることには違いなかった。
そして、このインドの旅に行くことを決意させた、最も大きな理由は、心の奥底に「できれば行きたくない」という気持ちがあったからだった。
今まで一人旅をしたことはない。
したいと思ったこともなかった。
一人で旅する人の心境が全く理解できなかった。
旅で出会う様々なことを、いつも誰かと共有したかったし、一人で受け止める自信がなかったのだ。
一週間も海外に居ると強烈なホームシックに掛かり、日本に帰りたくて仕方が無くなったことも一度や二度ではない。
海外に長く居ると、自分が一体どこに帰属しているのかが分からなくなり、自分の存在が突如あやふやなものとなって、猛烈な不安に駆られるのだった。
日本という国に妙にこだわったり、その昔、実家を売ると言う話が出たとき、もし金銭的に厳しいのなら、自分もローンの一部を出すから売らないでくれと父親に迫ったのも、恐らくそうした、自分の帰属している場所に対する執着や意識が強かったからだろうと思う。
一人旅の経験もなく、長い旅に出るとすぐホームシックに掛かり、英語が殆ど理解できず、人見知りが激しく、旅先ではいつもお腹を壊す。
もしかしたら、インドへ一人で旅をする、最もふさわしくない人間なのかもしれなかった。
なのになぜ、会社を二週間も休み、一人でインドに行くと決断できたのか。
実はチケットを取る直前まで、行き先をハワイかどこか南国の島でのバカンスに変更しようかと真剣に迷っていた。
しかし、楽しめそうなワクワクするような旅なら、恐らく仕事のことを考えて決断できていなかったと思う。
「できれば行きたくない」という、いわば試練と思える時間を過ごせると確信していたからこそ、立ち向かうべきだ、行くべきだと、自らを奮い立たせてインド行きが決断出来たのだった。
いずれにせよ、十年前に会社を辞めて独立した時、
「こんな自分でも十年やれたら長期休暇を取って、どこか放浪の旅に出掛けたい。行くならインドしかないな」
そんな漠然とした思いを、まさに実現しようとしている。
十年前にイメージしていた現在の自分と、今、自分が十年前を思い出していることが頭の中で交差し、夢と想いと現実とがまるで同時にそこに存在しているような、不思議な感覚が沸き起こってきた。
ふと窓から外を見ると、夕日の影を帯びたインドの地が目に飛び込んで来た。
平坦な土地に拡がる田園風景と、その合間に点在する村々を見ると、何もかもが平穏で、心をざわつかせる要因は何一つ無い。
自分は一体、この地の何を恐れていたのだろうか?ふとそんな疑問が頭をもたげてきた。
飛行機が着陸態勢に入ると、その疑問はますます強くなっていった。何を恐れていたのか?
疑問が強くなるに従い、逆に、自分は見えない恐怖に対して恐れを抱いていたんだということに気づき始めた。
ここインドで、どんなことが起ころうとも、それは見えない恐怖と戦うのではなく、現存する、目の前で起こるであろうことに立ち向かうだけなんだ。
これから始まる二週間の旅に、少しづつ胸が躍りはじめてきた。
四
世界の多くの国際空港がそうであるように、その国に多大なる貢献をもたらした歴史的人物の名を持つインディラ・ガンジー空港。
インドの首都デリーにある空港だ。
悪徳客引きが多いことで有名で、トラブルの多くはこの空港で起きていた。
旅の初めからトラブルに巻き込まれるのも嫌だったし、最初の関門はすんなりと通り抜けたいと思っていたので、日本から、空港からホテルまでの送迎依頼のメールを送っていた。
依頼先のインド人男性と電話で話はしたものの、連絡が途絶え少し心配していたが、空港へは約束通り迎えが来ていた。
空港は陰湿としており、外国らしい赤茶のライトがところどころ薄暗く灯されている。そして一歩空港の外に出ると、人力車のバイク版であるオートリキシャや、時代錯誤な形をしたタクシーのそばで、白目を光らせているインド人たちが客を待つために大勢佇んでいる。
辺りは砂塵にまみれ、空港の中でさえ野良牛が行き交っている。
野良犬ならぬ野良牛だ。
これが国際空港かと見間違うような雰囲気だ。
迎えの男に連れて行かれ、同じく時代錯誤なクルマに乗り込む。
シートは垢にまみれ、車内は泥と埃を混ぜて、そこらあたりに丁寧に擦り込んだような、思わずのけぞってしまうような素晴らしくインド的な匂いがする。
ホテルは、デリーの中心地であるコンノートプレースの近くにあった。
空港から約三十分ほどかけてホテルへ到着。
ホテルにチェックインした後、ツアー会社の小さなオフィスへ行った。
ツアー会社のオーナーからホテルに電話をもらい、夕食がまだならオフィスに来ないかと誘われていたのだ。
オフィスには、電話をくれた日本語の話せる、ビル・ゲイツ似のインテリ風インド人の他、数人のインド人が居た。
誘われるまま、カレーをつまみに日頃飲み慣れないバカルディを飲んだ。
翌日、そのツアー会社に頼んで、タージマハールを見た後、そのままアグラ駅まで送ってもらい、このベナレスへ行きの列車に乗ったのだ。
五
早朝、お願いしていたスペイン人の女性が起こしに来てくれた。
時計を見るとまだ四時だ。しばらくすると車掌も起こしにやってきた。
デッキに出てみると大きな駅が見えたので、そこに居たインド人に聞くと、やはりベナレス駅についたらしい。
アグラ駅を出発したのが夕方七時。同じ席のインド人が言ったように、到着の時間は大幅に違っていたが、九時間半かけてようやくヒンズー教の聖地ベナレスに到着した。
ベナレス駅のホームには、犬はいるし、寝転がっている男はいるし、自分で持参した七輪で炊き出しをする老婆もいて、本当にインドって何でもありだなと改めて驚く。
そして、そんな仄暗い駅のホームに立っていることが、とても不思議な感覚で、ニューシネマパラダイスの舞台となっていた映画館で、上映されていた古いムービーの中に、一人迷い込んでしまったような気分だった。
デリーで依頼した通り、しばらくすると迎えのインド人がやって来た。
白い時代めいたクルマに乗り込みホテルまで送ってもらった。
ホテルに着くと、迎えに来ていたインド人の若い男が笑顔をふりまきながら言う。
「サールナートに行かないか?仏陀が悟りを開いた後、初めて説法をした場所だ。
それにガンガー(ガンジス河)での、早朝と夕方に出るボードもある」
両方とも行きたい場所だったので、そのオプションツアーを頼むことにした。
ちなみに説法という英語はないらしく、ここだけ日本語でSEPPOHと言っていた。
今日はベナレスの町をゆっくり見たかったので、サールナートへ行くのは明日にしてもらい、とりあえず二時間ほど仮眠をしてから、地図を見て恐らくここがベナレスの最も賑やかな場所だろうと思われる、ダシャーワメード・ガートという沐浴場まで歩いて行くことにした。
ホテルを出ると、そこはまさに聞きしにまさるインドがあった。
行き交う人の群れ、乗せれるだけの人間を乗せた、人力車の自転車版であるリキシャと、けたたましいクラクションを鳴らしながら走るバイクやクルマ。
露店でチャイを飲む人たち。意味もなく佇む人たち。
制服を着てスクールバスで学校に通う子供たち。
学校に通うことなく泥と埃にまみれて店を手伝う子供たち。
のっそりと我が道を行く牛や道路の真ん中で寝そべっている牛。
餌を求めてさまよい歩く犬。
激しく舞う埃。
安っぽい油の匂いと、ゴミの匂い。
そこらあたりに落ちている牛糞の上を裸足で掛け声をかけながら歩く巡礼者たち・・・。
見えるモノ、聞こえる音、全てに驚きながら、約三十分ほど歩くと、ダシャーワメード・ガートに着いた。
話に聞いていた通り、インド人の客引きたちがやたらと声を掛けてくる。
「どこから来た?」「インドはどうだ?」「ベナレスにはいつ来た?」「インドには何日居る?」「ガイドが必要じゃないか?」
どれにも適当に相槌を打ちながら、とりあえず辺りをうろつくが、他に何をする当てもない。
さてどうしようかと思っていたら、さっき声を掛けてきたインド人客引きの一人が「火葬場はこっちだ」と言ってたのを思い出し、その方向へ歩いていくことにした。

しばらく一人で歩いていると、若いインド人が傍に寄ってきて、同じように質問してきた。
ガイドしてあげるがお金はいらない、とその若い男は言う。
もちろん下心があることは分かっていたが、しばらく彼に付き合うことにした。
彼の名はビッキー。
十八才だという。
本当かどうか知らないが、彼の兄の奥さんは日本人で、兄は日本の有名なアクターとフレンドだと言う。
半信半疑に話を聞きながら、彼と一緒に火葬場までやってきた。
火葬場の横には、以前マザーテレサのホスピスだった建物があり、その横に、火葬場を見る観光客のための大きな建物があった。
建物に入り火葬場を眺めると別のインド人の男が勝手にガイドを始めた。
彼によると、火葬される場所もカーストによって異なっているとのこと。
確かに、ビルの上に一つと、河沿いに二つ。そして、その下にもう一つの火葬場がある。
ビルの上の火葬場は、バラモンと言われる僧侶たちのためのもので、その下の二つが、クシャトリア(貴族・豪族・軍人など)、ヴァイシャ(商工業者など)。そして一番下が、シュードラ(農業労働者など)のための火葬場だと言う。
彼の話によると、伝染病で死んだり、コブラに噛まれて死んだ人間、妊娠中の女性、十一才以下の子供、そして火葬代のない人間は、焼かれずにそのまま河に流されるということだった。
火葬場で一日に焼かれる死体は約三百~五百体。一体に掛かる時間は約三時間。
「お前は日本人だから、人が死ぬと悲しむだろう?インドではガンガーによって生前のカルマ(業)が洗い流され、また転生してくると信じているので誰も悲しまない」
確かに焼かれる遺体のそばで遺族たちは平然とそれを眺めている。輪廻転生という考え方が骨の髄まで浸透しているのだろう。
ここに居ると燃えさかる炎を感じる程の近さだが、嫌悪するような匂いはなく、どちらかというと甘い匂いがしていくる。
次々と運ばれる死体と、焼かれている死体を見ながら、頭の中は真っ白で、どんな感情も浮かんでこなかった。
しかし、それは、何も感情が動かされなかった訳ではない。「人が焼かれる」という非日常な眺めに、沸き起こる様々な想いや感情の色が、あまりに強い光りとなって混ざり合い、真っ白になっていたのだった。
実は今年の正月、何十年か振りに書き初めをした。
何を書こうかと思い、ふと閃いたのが、「輪廻転生」という言葉だった。
この言葉が自分の中で明確に定着したのは、十代半ばに、三島由紀夫の“豊穣の海”という小説を読んでからだったと思う。
この小説の主題がまさに「輪廻転生」だった。
「そんな考え方もあるのか。」その頃は、漠然とそんな思いを描いたに過ぎなかった。
それから何年か経って、精神世界と自己探究の旅を描いた、アメリカの女優シャーリー・マクレーンの本から始まり、精神治療の権威でもあるエドガー・ケイシーなどの本を読み漁っていたこともあるが、自分の思想として深く根付いた訳ではなかった。
それが、昨年の暮れに父親が亡くなる辺りに掛けて、「魂」という概念であったり、「輪廻転生」という思想が再び大きく心を占めるようになっていた。
スピリチュアルカウンセラーとして有名になりつつあった江原啓行氏や、以前から興味を持っていた美輪明宏らの言葉を聞き、本を読み始めたことがきっかけだった。
そのタイミングと父の死期が重なり大いに救われた。
「魂は永遠なのだ」と思うと、父の死を素直に受け止めることが出来たのだ。あるいは、「輪廻転生」という概念で理解しなければ、父の死を受け止められなかったという方が、適切な表現かもしれない。
父親の葬式を終えた次の日に、「輪廻転生」という文字を書き、父が亡くなってから半年後に「輪廻転生」という考え方が日常にあるインド・ヒンズー教の聖地であるガンガーの火葬場を見ている自分の因果を考えると、何か見えない力によってこの場所に導いて来られたような気がしてならなかった。
もうしばらくここで人が焼かれる様子を見ていたかったが、同じように眺めていた白人たちが次々と去っていくので、頃合いを見て立ち去ることにした。
昨日の晩から何も食べていないことに気が付き、ビッキーとガンガーフジレストランという食堂に入った。
チキンカレーとペプシとミネラルウォータを頼んで九十ルピー(二百三十円)。
ビッキーの案内で周辺にある寺院を見て回ったのだが、二度と行けないような入り組んだ細い路地をぐるぐる周り、汗だくになっていた。
途中チャイを飲んで少し休憩し、ビッキーの兄の店に行くことにした。
道端で売っているチャイは、三ルピー(八円)。しかしこれは外国人価格らしく、インド人であれば一ルピー(三円)で飲める。
この外国人価格というのはインドにはどこでもあって、前日に行ったタージマハールの入場料は、インド人が十ルピー(二十六円)で、異国人は百ルピー(二百六十円)となんと十倍もの値段の差になっていた。
ビッキーの兄の店は、ダシャーワメード・ガートの目抜き通りに面したビルの一階にあった。
シルクなどを扱う土産物屋だ。
兄の名はムケ。
年齢は二十五才。
彼は日本語が上手く、逆に英語があまり得意ではないというめずらしいインド人だった。
聞くと、何年か前にテレビで放送されていた沢木耕太郎の「深夜特急」のドラマ版に出演した経験があるという。
色々話を聞いていると、この話はどうやら本当らしかった。
ビッキーが言っていた「兄は日本の俳優と友達だ」というその俳優は、沢木耕太郎を演じていた大沢たかおのことだったのだ。
しばらくその店で雑談し、チャイやサモサをご馳走になった。
夕方のガンガーで船に乗る約束をしていたことを思い出し、リキシャでホテルに戻ることにした。
あらかじめ相場は十五ルピー(四十円)と聞いていたので、交渉してその値段で行って貰った。
しかし、ホテルに着いて二十ルピー札を渡すと、リキシャの男は「五ルピーはめぐんでくれ」と言う。
インドで甘い顔は禁物だと思い、「いや、ちゃんとお釣りを払え」と三回くらい言うと、やっと払ってくれた。

ホテルに着くと、朝とは別の男が待っていた。男は二人組で、片方はやたらと背が高く、片方はやたらと背が低い。
まるで漫才コンビのセントルイスだなということで、勝手にセントルイスと呼んでいた。背の高い方(セント)は日本語も英語も話せず、もっぱら運転手役。
背の低い方(ルイス)は、英語が話せるためガイドをするという役回りだった。
クルマで十分ほど走り、あるガートに着いた。そのガートの横にも火葬場があり、こちらは小さい方の火葬場で朝見た方がメインの火葬場だとルイスが説明してくれた。
小さな船に一人で乗り込むと、漕ぎ役の男の他に、花を売る少年が乗り込んできた。
少年によると、自分の大事な人への想いを込めて、花の中央にあるローソクに火を点けてガンガーに流すのだという。
船を漕ぐ男はインド訛の強い英語で、
「何時間回る?スタンダードは二時間だ。どうする?」と聞くので、二時間は長いと思い一時間乗ることにした。
船は朝行った火葬場の方まで行き、焼かれている遺体のすぐ側まで近づいていった。
そこから見えるのは、シュードラ(農業労働者など)の焼かれる場所だった。
燃えさかる炎の中から露出した足が見える。
すぐ横の大きなボートに乗っていた白人の団体客も、人が焼かれるところを初めて見たのだろう、
皆神妙な顔をして、その炎や、焼かれている横で遊ぶ子供たちや、その周りをうろつく犬や牛を凝視していた。
ガートへ戻る途中、昼間の暑さが嘘のようにガンガーを爽やかな風が通り抜ける。
夕方のガンガーは昼間の喧噪とは違い、とても神聖な雰囲気になっていた。




ちょうど一時間で元のガートまで戻ってきた。
船から上がると、別の太ったインド人の男が金を払えと言っている。
ホワイ?と聞くと、
「船の料金は三十分の乗船分しかもらっていない。お前は一時間乗ったのだから延長した分を払え」と言うのだ。
また金かと思いながら、つたない英語で反論した。
「俺はすでにツアー会社にこの船の料金は払っている。欲しいならツアー会社から貰え!」
そのやりとりを横で聞いていたルイスがたまりかねて、まぁまぁまぁといった感じで仲裁に入り、その場は収まった。
あやうく必要の無い金を払わされる所だったとムスッとしていると、ルイスが笑顔で言った。
「アーユーハッピー?」
実は、この後何度もこの言葉を言われる羽目になる。
ホテルに戻りレストランで食事をした。
ミックスベジタブルカレーとラッシーとミネラルウォーターで百ルピー(二百六十円)。
朝、湯が出なかったので、これまた訛の強い英語しか話せないフロントのネパール人にその旨を言うと、
「シャワーは何時から入る?その時間には出るようにする」と言う。時間制かよ、と思いながら、部屋に戻ってシャワーを浴びたが、湯というより、ちょっとなま暖かい水が出るだけだった。しかし、これもインドかと思って諦めた。
その癖、しばらくすると、ネパール人は部屋に電話をしてきて、シャワーの湯はちゃんと出たか?と聞く。
文句を言う気はすっかり失せていた。
「大丈夫、ちゃんと出た。ありがとう」
そう言って電話を切った。

六
翌日は、朝のガンガーを見るために再び船に乗る予定だった。
ルイスは朝の五時半に迎えに行くと言っている。目覚まし時計を持ってきてないため、
「起きる自信がない、まだ起きてなかったら部屋をノックして起こしてくれないか」と言うと、
「そんなことは出来ない。マナーに反する」
仕方がないので腹時計に頼ることにした。
しかし結局はあやふやな腹時計。
やはり気になって、翌朝は何度も目が覚めた。
約束の時間に近づいてきたので、そろそろ起きようかと思っていると、部屋の電話が鳴った。
ルイスが心配してホテルのスタッフにモーニングコールを頼んでくれていたのだ。
昨日と同じガートまで連れて行ってもらい、船に乗ろうとすると、昨日金を払えと文句を言ってきた太った男が近寄ってきた。
「何時間乗るんだ?三十分以上だと延長料を払ってもらう」
なら三十分でいいと言って船に乗った。
船は昨日とは違う南へと進んでいった。
ここベナレスは、壮大なガンガーの流れの中で唯一、南から北へと流れていく場所である。
そういう点で、長いガンジス河の中でも神聖な場所とされていると聞いたことがある。
あるインド人の男に、「ガンガーはどこから流れてくるか知っているか?」と聞かれたので「いや分からない。
でも、確か二つの河が交わってガンガーとなると聞いたが」と言うと、「違う。シヴァ神の頭から流れてきているのだ」とその男は笑いながら言った。
朝のガンガーは昨日とは違い、それぞれのガートでは老若男女が入り乱れて、沐浴をしたり、歯を磨いたり、口を濯いだり、洗濯したりしている。
そのすぐ横には火葬場があり、河の中央には、大きな牛の死骸がゆっくりと流れている。
聖なるものとは一体何なのか、俗なるものとは何なのか?この状況を見てそう考えない異国人はきっといないだろう。
ベナレスに住む人たちの日常は、まさに神聖なものと俗なるものが背中あわせに存在し、生と死が強烈な生々しさで混在している。
インド人におけるヒンズー教徒の割合は約八十%以上。
その聖地がこのベナレスであり、ガンガーである。皆、この河の水でこの世のカルマを洗い落とし、この河のそばで死に、死んで焼かれた灰をこの河に流して貰うことだけが、現世の望みなのだ。

町中にある現地の人が利用する食堂で朝食を取った。
プーリーと言われる小麦粉を揚げたものとカレー汁のようなもの。
そしてチャイ。それだけで二十ルピー(五十二円)だった。
インドに来て、すっかりチャイの魅力に取り付かれていた。
暑い最中に飲む、甘いミルクティーが、こんなに美味しいとは思わなかった。
しかし、日本で飲むとまた違った味なのだろう。このインドの地で飲むからこそ、旨く感じるのだ。
朝食を終えサールナートへ向かう。
サールナートは、ブッダガヤで悟りを開いた仏陀が、初めて説法した場所で、ここで仏陀の説法を聞いた五名の僧侶たちが、仏教の教えを全世界に広めたと言われている仏教の聖地の一つだ。
聖地らしく、日本寺の他、チベット寺、韓国寺、中国寺などがあるが、日本寺以外は、南国特有のカラフルな色使いでどうも馴染みにくい。
途中、目の見えない子供を抱いた母親が、子供を指さしながらお金を恵んでくれとゼスチャーする。
インドに行ったら、決してお金を恵むまいと決めていた。
しかし、その親子を見てその決心が緩みそうになった。
しかし、なぜそんな決心をしたのかは覚えていない。
別にお金が惜しい訳ではない。
少なからずのお金でその親子は食事にありつけることができるかもしれない。
親子はその施しを頼りに生きているのだ。
体の動かない老人ならまだしも、若い母親が施しで生計を立てているということに憤りを感じつつ、その母親の目を凝視することができなかった。
ベナレスの町中でも、托鉢を持ったインド人の老人に、いちいち立ち止まって施しをする西洋人を見て、はっとさせられ、頑なに施しをしないと決めていたのは何故だったんだろうと考えたこともあった。
インドに行くと、「もう一度行きたい」と思う人と「二度と行きたくない」と思う人の二つに分かれるとよく言われる。
インドに行きたいと思っていた十数年前から、自分は絶対に後者だと思っていた。
インドでは厳しいカースト制度によって、下層の人たちはどんなに努力しようとも豊かな生活は得ることができない。
だからこそ「輪廻転生」という思想が生まれたのだと思う。今世でどんなに努力してもカーストによって人生が決められている。
なら、来世にその希望を託したいと考えるのはごく自然だからだ。
しかし、その自分をありのままに受け止め、貧しい生活を余儀なくされ、ただ無為に人生をやり過ごす人たちを見て、自分は正常で居られるだろうか。この世の、ずっと知らないふりをしていた現実を見ることで、自分を見失い、生きる目的を失ってしまうのではないか。
だから、インドに行っても何も正視できず、「二度と行きたくなくなる」のではないか。
そう考えていた。


十数年前の思いが、貧しい親子を見て甦ってきた。
そして、結局は目を逸らせることしか出来なかった。
サールナートからの帰り道、激しい自己嫌悪に陥っていた。
そんなことを知る由もないルイスが後ろを振り返り、
「オフィスによっていく」と言うので、イエスという返事の変わりに、インド人がそうするように少し首を傾げた。
オフィスには昨日の朝、駅まで迎えに来ていたインド人が居た。
どうやら彼がボスのようだ。
そのインド人たちとテーブルを囲んで座っていると、その若いボスが早口の英語で言った。
「×××ホテルからブッダガヤ駅までピックアップする。もちろんお金はかからない」
×××ホテルという名は聞いたことがないし、早口でよく理解できなかった。
何度尋ねてみても理解できない。
痺れを切らした若いボスは、分厚い予約帳のようなものを取り出して、あるページを指さした。
見るとそこには自分の名前が書かれてある。そしてボスは当たり前のように言う。
「ここにお前の名前が書いてある。すでにホテルをブッキングしている」
つまりこういうことだ。次に行く予定にしているブッダガヤで宿を(勝手に)取った。
そして、駅からそのホテルまでの送迎をしてやる、ということなのだ。
もちろんブッダガヤの宿の予約を依頼した覚えはない。
それどころか、ブッダガヤの宿が決まっていないのなら、こちらで予約してやるという申し出を、昨日の朝、はっきりと断っていたのだ。
英語がよく分からないこと良いことに、勝手にホテルを予約して、「ピックアップはフリー(お金がかからない)」という部分だけ強調して、もしこちらが「フリー」という部分だけを理解して「オーケー!」と言おうものなら、後で「お前はオーケーと言ったではないか」と、金を払わす魂胆なのが分かった。
さすがにカチンときて、「ブッダガヤのホテルは頼まないって、昨日、言ったよな!」とスゴむと、若いボスは、さすがに形勢不利と見たのか、それには答えず「チャイを飲むか?」と、まるで何事も無かったように言った。
腹の虫が治まらず、そのオフィスを出て、ルイスに言ってやった。
「お前のボスは嘘をついた。信じられない。お前のボスが嫌いだ!」
「あれは俺のボスじゃない。俺には誰もボスがいない」
つまり、雇われガイドという訳だ。しかし、この手で数多くの英語が苦手な日本人がカモにされていたのだろう。
不機嫌な顔をしているとルイスがまた言った。
「アーユーハッピー?」
サールナートで会った母親の目と、オフィスでのやりとりを終えて、インドの空恐ろしさを実感して、すっかり意気消沈してしまった。全く持ってノーハッピーだ。
それどころか、とうとう始まった。
「あと何日このインドに居なければならないのだ?二週間のうちまだ三日しか経っていない。日本に戻れるのはあと十日も後だ。それまでこんな国で過ごすことが、自分には本当に出来るのだろうか?」
すっかりホームシックになっていたのだ。
沈鬱な想いのまま、クルマに揺られていた。
クルマはインドのシルク工場へ向かっていた。
シルク工場は暗い湿気たっぷりの建物で、中には小さな子供たちが鶴の恩返しのような機織り機でシルクを織っていた。
日本では手作りの方が高価だが、インドでは機械で作る方が高くなるらしい。
それほど人件費が安いのだろう。子供たちは、見慣れない東洋人を見て、人懐っこい笑顔でハローハローと近寄ってくる。
工場をいろいろと見学した後は、「やっぱり」と思ったが、商談室みたいなところへ連れて行かれた。要するに買えということなのだ。
シルク工場のインド人社長と、その番頭らしき若者の二人が出てきて、愛想を振りまきながら色々話掛けてくる。
しかし、彼らはの英語はインド訛が強くて殆ど意味が分からない。
「あなた達の英語は、インドスタイルでよく分からない」と言うと、ルイスが彼らの言葉を通訳してくれた。と言っても、英語から英語だが。
「俺の英語は日本スタイルだからよく分かるだろ?」
とルイスが言うので「確かによく分かる」と答えるとご満悦の様子だった。
インド人社長とインド人番頭は、シルク製品を一通り披露した後、
「どれか気に入ったものはあるか?」と言う。
もちろんこっちには買うつもりが全く無いので、
「悪いが、ショッピングツアーで来ている訳ではないし、お金もあまり無いので買わない。」と言うが、全く引き下がる様子はない。
その後、何度「ノーバイ!」と言っただろうか。
しまいにルイスが、インド人社長にヒンズー語でなにやら話し、やっと引き下がってくれた。何と言って納得させたのは分からなかったが、
「この日本人はまったく買う気がない。無理に買わそうとしても無駄だし、それは良くないことだ」みたいな感じだったのだろう。
その後、懲りもせずルイスは別の土産物屋でクルマを停めた。
「何も買わないよ」と言うと、「とりあえず見てくれ」とのこと。
多分、連れて行ったらマージンが貰えるか、面目が立つのだろう。
その土産物屋の主人は人の良さそうなインド人で、日本語で話し掛けてきた。
「何か欲しいですか?」
「何も買わないし、買う気がない」
「今日、朝から初めてのお客さんなのに、何でやねん」
なんと関西弁ではないか。さすがに笑ってしまったが、ここは負けじと「知らんがな」と言って店を出た。
昼飯を食べようということになり、遠藤周作の小説「深い河」の舞台となった、ホテル・ド・パリの横にあるレストランに入った。
チキンカレーとラッシーとミネラルウォーターで百ルピー(二百六十円)。
その食事中、今度はルイスが真面目な顔をしてこう言い始めた。
「自分のガイドはどうだった?もし不満がないのなら、チップとして五百ルピー(千三百円)くれないか?」
「インド人は何かと言うと、すぐ金・金・金だ。俺はあんたのボスと取引してお金を払った。あんたはボスと取引しているんだろう?ならボスから金をもらうのが筋だ」
「いやボーナスみたいなものだ」
「ノーボーナス!」
そう言うと、しばらく沈黙した後、
「俺には家族が居る」と来たので、
「俺にも家族が居る。同じだ。とにかく払わない」
きっぱりと言うと、ルイスは急に落ち込み始めた。
今度はこっちが聞く番だ。
「アーユーハッピー?」
「ノーハッピー!」
完全に拗ねてしまったようだ。
帰り道、ずっと拗ねていたルイスと別れホテルに戻った。
少し仮眠し、夕方からいつものガートまで歩いていった。
昨日見つけたインターネットショップに寄り、メールを送る。
約三十分利用して十ルピー(二十六円)。
そのまま、細い入り組んだ路地を通り抜けて、小さい方の火葬場へ行くが、ここでは、なかなか一人にはさせてもらえない。
何人ものインド人が声を掛けてくる。どれも適当に返事をして、しばらく火葬場を見ていると、またしても変なインド人が寄ってきた。
いつもの通り、どこの国から来たとか、いつまでこの町にいるのだとかと聞かれる。
一応返事をしていると、そのインド人は「私は日本のギャグを知っている」と言った後、「コマネチ!」とか「アンガールズ」とか微妙なところを言ってくる。そして、また何かの問いに答えると、ここだけ日本語で、
「分かった。カルカッタ!」とアホみたいなオヤジギャグを言う。ちょっとおもしろかったが、何度も言うので飽きてしまい、「じゃまた」と言ってダシャーワメード・ガートへ向かった。
途中、昨日ムケの店に居た若いインド人と合流。
若いインド人は二十二才で、名前をサンジュといった。
ムケの店の客引きが彼の仕事だ。
サンジュによると、今はヒンズー教の祭りの月で、今日もこの場所でセレモニーがあるという。途中、初めて日本人を発見。女性三人組だ。もちろん話掛ける訳もない。
しばらくしてセレモニーが始まり、ずっと見ていたが、雨が降り出したので退散し、サンジュと晩飯を食べるため食堂へ行った。
サンジュによると、今の時期は韓国人とスペイン人、フランス人の観光客が多いらしい。日本人は八月が一番多いのだと言う。お盆休みを利用した客なのだろう。
店では、ミックスベジタブルカレーとナンとラッシー。そしてサンジュの食事も合わせて九十四ルピー(二百五十円)。
食事を終えても、雨は止むどころかスコールになっている。
細い道はまるで川のようで、大きな道に行くと、水がくるぶしまで来ている。大洪水だが、インド人たちは普段通りの様子だ。
リキシャも、雨の特別料金ということで普段の二倍以上の四十ルピー(百円)。ホテルまで帰る途中は、もう訳が分からない位に大渋滞。
人とリキシャとクルマと単車がこれでもかという程に入り乱れて、そこらじゅうのクルマやバイクはクラクションを鳴らしまくっていて、もう凄い状態だった。
なんとかいつもの三倍くらいの時間を掛けてホテルへ到着。
ホテルに戻っても、昼間の母親の目や旅行会社のボスとのやり取りが頭から離れることはなかった。
こんな国から早く退散して、日本に帰りたい。
それが今の率直な気持ちだった。